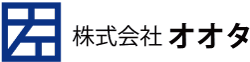今の時代は、風の時代だと呼ばれている。聞いたことがある人もいるだろうが、この「風の時代」という言葉について、ひも解いてみたいと思う。実はこの言葉、占星術から来ていて、時代を200年ごとに特定の星座が人間社会に影響を及ぼす、という考えである。
2020年12月22日から、今は、風の時代に入っているという。それまでの200年は、「土の時代」であった。星座で言うと、おとめ座、やぎ座、おうし座の時代だった。土の時代の特徴は、物質、金銭に価値があり、この世の成功は、お金持ち、物質をたくさん持った人達だった。200年前の世の中は、産業革命から始まって、人々は、豊かさがステータスな世の中になってきたのである。
しかし、「風の時代」は、目に見えないものに価値が移っていく。情報や、コミニュケーション、スピリチュアル、波動、といったことに価値観が移っていく。これは、いったい何を意味するのだろうか?星座で言うと、みずがめ座、ふたご座、てんびん座の影響する時代であると言われている。
例えば、物事を始めるにあたって、情報は非常に大切のものだ。人は情報に基づいて行動するが、どんな情報を取り入れるかによって結果が変わってくる。誰かが、
「農業は良いよ。今からの時代に合っているよ、それも、無農薬でやらなくちゃ。」と、言ったとする。
確かに、それが正論である。しかし、現実に農業をやったことがある人なら分かると思うが、無農薬でやると、他の畑や田んぼから害虫がたくさんやってくるのである。それに対応するためには、たくさんの農地を借りて作物を栽培することは難しい。周りの農地は、化学農薬がたくさん使われており、そこから害虫がやってくるのである。また、流通のルートでJAを利用するとすれば、どんなに品質の良い無農薬の野菜を作ったとしても、他の農家の金額と同じになってしまう。生産性が上がらないのだ。また、農業を始めるのには、少なくとも、3千万~4千万円は、かかる。
こうした情報まで分かったうえで、農業を始めなくてはならない。一般のマスコミで言っていることに影響されていてはならない。
情報だけ取り上げてみても、正確な情報がいかに必要であるかが、わかるであろう。コミニュケーション、スピリチュアル、波動、といったことについては、また、別な機会に取り上げていきたいと思う。
いずれにしても、今は、「風の時代」である。価値観が変わってきている。そのことを踏まえて、これからの人生を作っていくことが必要であろう。