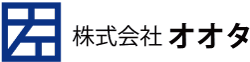季節の変化をよくわかるように日本字は昔から暦を使ってきた。二十四節季と言う言葉を聞いたことがあるだろうか。二十四節気(にじゅうしせっき)は、今でも立春、春分、夏至など、季節を表す言葉として用いられている。1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたもので、「節(せつ)または節気(せっき)」と「気(中(ちゅう)または中気(ちゅうき)とも呼ばれる)」が交互にあるものだ。
ちなみに、3月6日は、啓蟄と呼ばれ、啓蟄のことばの意味は、寒さが緩んで春の陽気になってくることによって、土の中から虫たちが動き出す季節のことを指す。 「啓」という字はひろく、「蟄」は土の中で冬ごもりしている虫のことで、春を感じた虫や、冬眠していた生き物たちが続々と動き出す、そういう春を感じる言葉である
虫が動き出す時期のことだ。人々の活動も春から動き始めてくる。今年、4月には、新入社員が7名、オオタに入社予定である。会社の社員として、また、社会人として活動を始めるのである。その新入社員を歓迎するために会社で歓迎会を開くことがあるだろう。その時は、新入社員が会社の中で仕事を成功していく姿を見ることが出来るようにしていきたい。
予祝と言う言葉がある。未来の姿を先に喜び、祝ってしまうことで 現実を引き寄せることを「予祝(よしゅく)」と言う。 平凡社の『世界大百科事典』には、次のように説明されている。 「豊作や多産を祈って、一年間の農作業や秋の豊作を模擬実演する呪術行事。 農耕儀礼の一つとして〈予祝行事〉が行われることが多い。」
4月の会社歓迎のパーティは、この予祝になればいい。